レーザーセンサー (フロント) について
この車両にはレーザーセンサー (フロント) が装備されています。レーザーセンサー (フロント) は次のシステムが共有しています。
-
スマートシティブレーキサポート (SCBS)
-
AT誤発進抑制制御
-
スマートブレーキサポート (SBS)
レーザーセンサー (フロント) は、フロントガラスの上のルームミラー付近に設置されています。
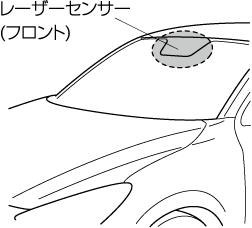
各システムの正しい作動のため、レーザーセンサー (フロント) 付近のフロントガラス表面は、いつもきれいにしておいてください。

-
各システムの正しい作動のため、次のことをお守りください。
-
いつもフロントガラスをきれいにしてください。
-
フロントガラス表面にステッカー (透明なものを含む) などを貼り付けないでください。
-
飛び石などでフロントガラスのレーザーセンサー (フロント) 周辺に傷などが認められるときは、ただちに各システムの使用を停止し、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。
作動を停止させるときは次のページを参照してください。
→参照「設定変更 (カスタマイズ機能)」
-
フロントガラスにガラスコーティング剤などを使用しないでください。
-
フロントガラスやフロントワイパーを交換する際は、マツダ販売店に相談してください。
-
センサーは絶対に取り外さないでください。
-
取り外したセンサーはIEC 60825-1規格におけるレーザー等級1Mの条件を満たしませんので、目に対する安全を保証できません。
-
センサーから100 mm以内の距離で、拡大鏡・顕微鏡・対物レンズなど拡大機能がある光学機器を使用して、センサーをのぞき込まないでください。
-


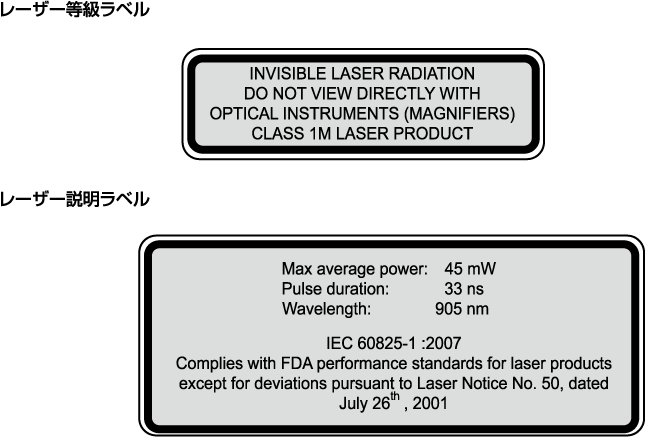
レーザーセンサー放射線データ
最大平均出力: 45 mW
パルス幅: 33 ns
波長: 905 nm
発散角 (水平×垂直): 28°×12°
次のような場合は、レーザーセンサー (フロント) が前方車や障害物を検知できず、各システムが正常に作動しない場合があります。
-
フロントガラスが汚れているとき
-
ルーフレールなどを装着してレーザーセンサー (フロント) をおおうような長尺物をのせたとき
-
前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき
飛び石などでフロントガラスに傷などが認められるときは、フロントガラスを必ず交換してください。交換する際は、マツダ販売店にご相談ください。




 はじめにお読みください
はじめにお読みください










